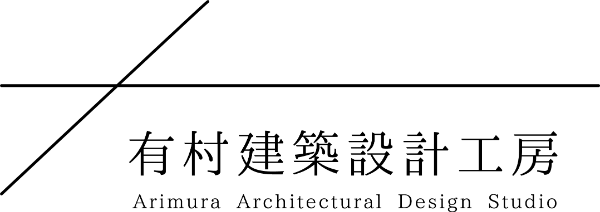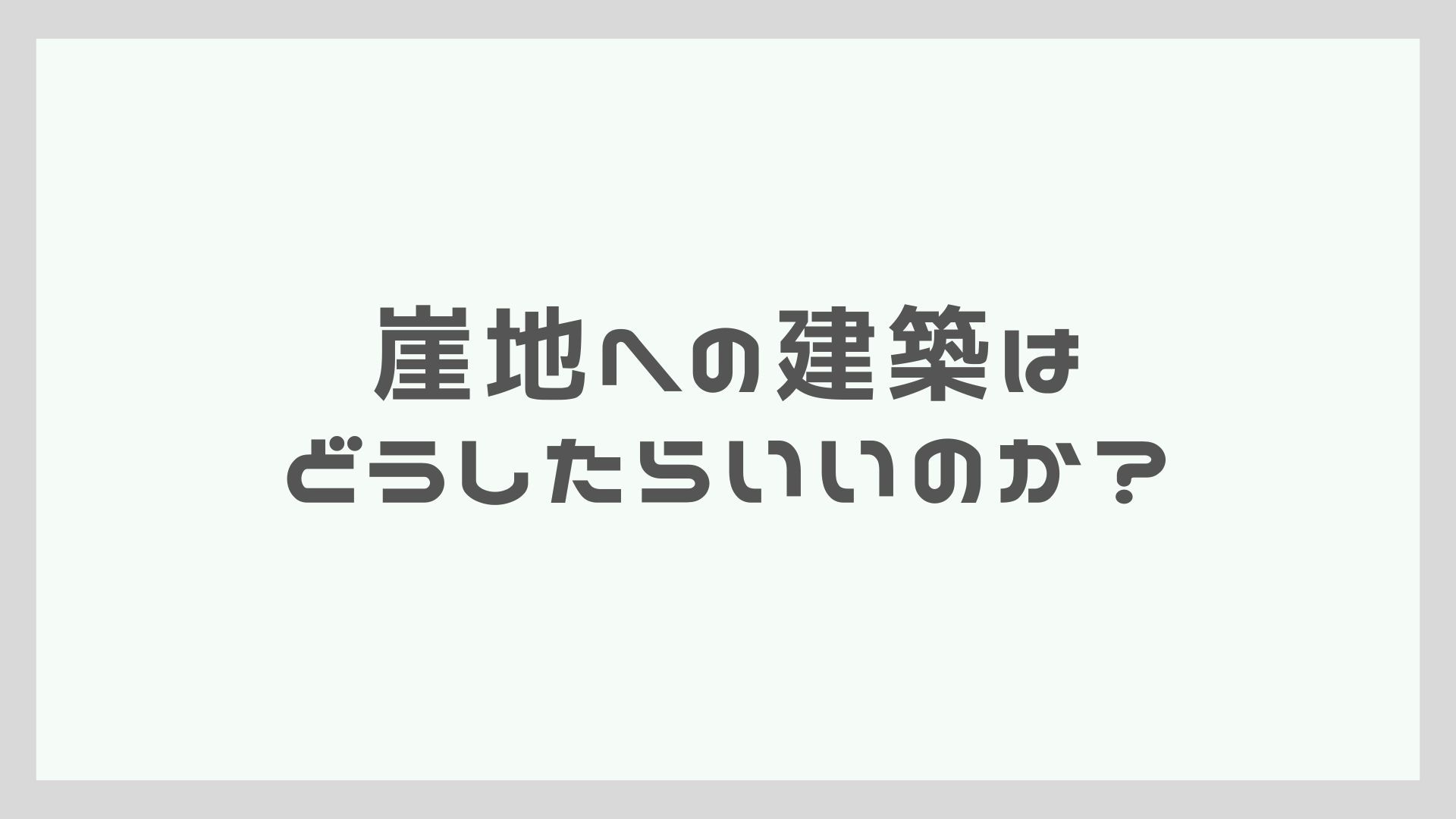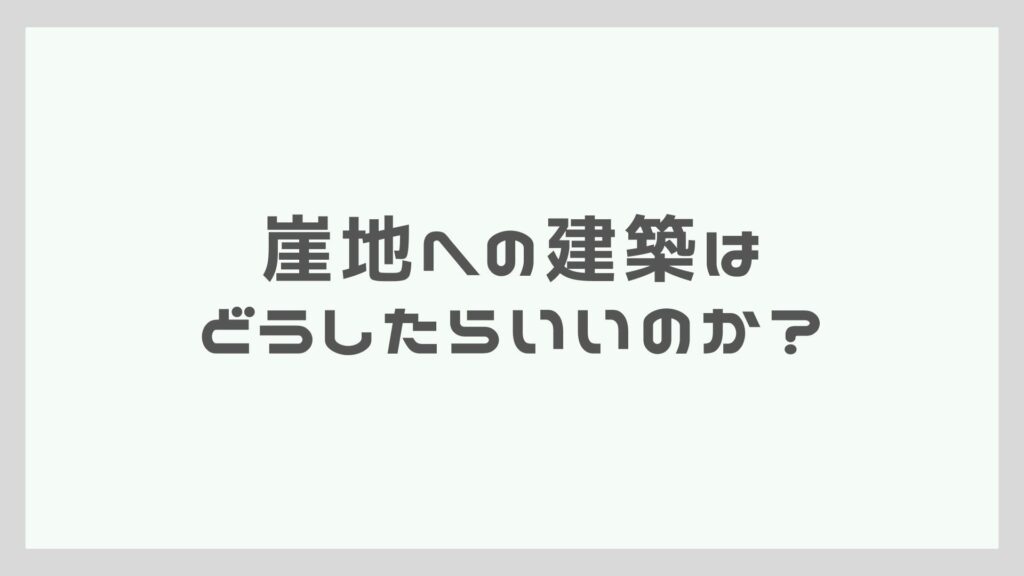
土地を探していると時に以上に安い土地があったりします。
土地の位置図だけを見るとなんてことはない普通の土地だと思っていたけど見に行ってみたらとんでもない高低差が。。。
なんてことがあります。
高低差だけならいいのですが、その高低差が崖と認定されてしまうと建築に対してかなりの制限をかけられてしまいます。
そんな崖地ですが、結論から言うと「そんな危険なところで建てないで!」です。
しかし、事情によっては崖地に家を建てないといけない場合もあると思います。
その場合はどうしたらいいかご紹介していきたいと思います。
では、そもそも崖とは何でしょうか?
それについては各都道府県が崖についての条例を施行している事が多いです。
僕が拠点にしている鹿児島県でも【建築基準法施行条例(昭和46年鹿児島県条例第33号)】にて崖の記載があります。
・第3条建築物が高さ2メートルをこえるがけに近接する場合は,がけの上にあつてはがけの下端から,がけの下にあつてはがけの上端から,建築物との間にそのがけの高さの2倍以上の水平距離を保たなければならない。
・2鉄筋コンクリート造等の重量建築物をがけの上に建築しようとする場合にあつては,前項の数値を安全上支障がない程度に増大しなければならない。
・3前2項の規定は,建築物の用途,規模若しくは構造若しくは擁壁の設置又はがけの状況により建築物が安全上支障がないと認められる場合には適用しない。
と記載があります。
簡単に言うと「がけ」とは地表面が水平面に対し30度を超える角度をなし,かつ,その高さが2メートルを超える土地をいう。
との事。
この条件に当てはまるのが崖になります。

※鹿児島県がけに近接する建築物について出典
基本的に30度のラインより急な角度になっているのが崖でその崖との高低差の2倍の範囲には建築不可になっています。
これが崖の基本です。
そこから建築の許可を得るために確認申請を出すのですがその為に崖相談という相談を確認申請を提出する行政庁もしくは指定民間機関にしなければなりません。
ここからが少し厄介なことがあるのですが。
崖と認定する条件は先ほど紹介した通りなのですが、その崖に対して建物が建てれるようにする為の対策は各申請の提出先で大きく違ってきますので注意が必要です。
対策の取り方によっては
A申請先ならOKなのにB申請先はNGなんてこともありえます。
申請先は確認申請を提出する建築士によってそれぞれです。
審査が早かったり、審査官と関係が良好だったり、ある程度融通の利く審査機関だったり、審査の癖を把握しているところだったりと本当に様々です。
なのでここで紹介する方法が必ずしも対策として有用ではないことがあるという事は念頭に置いておいてください。
対策1:崖になっている高低差の部分に擁壁を作る
一番簡単でその土地に自由に家を建てれる方法として擁壁を作るという事です。
高低差の大きい土地だとコンクリートの壁や斜めにブロックが積まれているところを見たことがあるかと思います。
これは擁壁や間地ブロックと言って、土が崩れないように土留めをする構造物です。
これがあるとそもそも崖崩れのリスクが減る為、その上の崖の規制が緩和され自由に建築可能になります。
費用さえ捻出できれば崖についての心配からは解放されます。
古い土地だと土地購入時点で擁壁や間地ブロックがあればそれを再活用して崖の規制を緩和することもできます。
しかし、注意点もあります。
古い土地の現状の擁壁や間地ブロックを使う場合は必ずその製造年月日と現状の状況把握が必須になります。
製造年月日はその擁壁の工作物申請完了検査済証や宅地造成許可、開発完了検査済証などから確認することができます。
裏を返すとこれらが確認できない場合は例え擁壁や間地ブロックが残っていたとしても崖の規制緩和に使う事が出来ないという事になります。
稀にこの事を施主に伝えずに土地を売っている不動産屋さんもいますので注意が必要です。
また、例え許可や完了検査済証があったとしてもその擁壁や間地ブロック自体にヒビがあったり、ゆがみが出ていたりすると申請先から却下される場合があります。
崖の相談は建築士の責任のもと、建築士のみが行える業務なので擁壁があっても必ず建築士へ相談した上で購入を検討するようにしてください
対策2:深基礎や杭でを作る。
自身の家を崖の上に建てる時の対策です。
先ほど崖は2M以上の高低差と30度以上の角度がある場合に崖になるとご紹介しました。
この30度の事を一般的に30度ラインといいその内側を安息角と言います。
そしてこの30度ラインより上が崖が崩れた時の危険ラインとなります。

※建築家紹介センター出典
なのでこちらの画像のように崖が崩れるであろう範囲より深く基礎を作った場合は崖が崩れても家が共に崩れ落ちることなく残る事が出来ます。
深基礎の他にも杭を打つ方法もあります。

※建築家紹介センター出典
杭も構造上は基礎なのでこのように30度ラインより下まで杭を打つことで崖が崩れても建物は杭上に残る事ができるので建築が可能となります。
ここで注意が必要なのは鹿児島県の杭工事は少し事情が違うという事。
鹿児島県の場合、杭工事と言えば地盤改良が出た時にする砂利杭をイメージする人が多いですがこれはNGです。
砂利杭は地面と砂利の摩擦で家を支える杭なので崖が崩れたら共に砂利杭も崩れ落ちるので意味がありません。
崖対策で言う杭とはコンクリート杭や鉄柱の杭の事を言いますのでご注意ください。
対策3:高基礎を作る又はRC住宅にする。
対策2は崖上の対策でしたので次は崖下に家を作る場合の方法です。
崖下に家を建てる場合は土が上から崩れてきた時の対策が必要になります。
崖上から30度ライン外から離すというのが一つともし建物が30度ラインの内側になってしまった場合は部分的に基礎を高く作り家が土砂で壊されないよう対策します。

※建築家紹介センター出典
木造の建物や鉄骨の建物はどうしても外からの質量的圧力には弱くなってしまうのでそれを基礎のコンクリートを使って壊れないようにしてあげます。
なので裏を返すと崖下に家を作るにあたっては鉄筋コンクリート住宅を作ること自体が対策になりえます。
対策4:崖から離す。
最後に一番基本的な対策として崖から建物を離すという事です。
崖の30度ラインにかからない位置や崖の高さの2倍離すことが出来たらより安心です。
これにはコストもかかりません。
しかしこれには崖との距離を取るというかなりの敷地面積が必要となります。
場合によっては希望の大きさの家が建てれないなんてこともありえます。
何度もお伝えしますが、崖地に家は作るものではないというのが僕の結論です。
もし災害に合ったら元も子もありません。
それでも崖地に家を建てないといけない理由がある方はこの対策を念頭に建築するために対策する費用を踏まえて考えましょう。
もし、他の土地が安いからと安易に考えている場合は崖の対策で蓋を開けたら他の土地より高くついたなんてこともあるという事を覚えておいてください。
それでも崖地で建築計画をするなら、自分たちだけで土地を購入しない事、必ず建築士に土地を見て貰った上で相談して購入する事(ハウスメーカーの営業はダメです)不動産の土地情報に崖の表記がされている事を必ず守ってください。
崖に建てるべきではないと話しましたが、崖上の場合はその景観の良さから人気な場所の一つであるのも事実です。
状況をしっかり把握し、対策を万全に言い家づくりができるよう有村建築設計工房では家づくりのお手伝いをしています。
結局のところ障害の多い土地ほど建築家としてはワクワクしてしまうのも事実です(笑)
崖でお困りでしたらぜひ一度有村建築設計工房にご相談ください!